MENU




【森永製菓】プロテイン公式サイト > 健康なカラダでいたい > 運動でカラダが衰える!?高齢者の健康維持には正しい栄養摂取が必要



「いつまでも元気に健康なカラダでいたい」と思う方は多いのではないでしょうか。しかし、年齢を重ねていくにつれて、誰でも身体能力の低下をはじめとしたカラダの機能が衰えていきます。身体能力の低下予防に、運動をしている高齢者の方もいると思います。
本記事では、高齢者の栄養摂取と運動について解説します。
※記事内でご紹介している森永製菓の製品の栄養成分は、2024年12月23日時点のものとなります。
日本では一般的に65歳以上を高齢者と定義しています。令和4年の国民栄養調査の結果では、高齢者の中でBMI20以下の低栄養傾向の者の割合は男性12.9%、女性22.0%でした。
BMIは体重と身長から計算される体格指数です。体重が減少する原因の一つには、食事量が減り、カラダに必要な摂取エネルギーが減少していることが考えられます。また、カラダに必要な摂取エネルギーが不足した状態で運動を行うと、さらに体重が減少してしまいます。
高齢者が健康を維持していくためには、カラダに必要な栄養素を摂取し、個人が目標とする体重を維持することが大切です。また、自分に合う適度な運動を行いながら、身体機能を維持していくことも同時に考えてみてはいかがでしょうか。
健康維持のために目標とする体重はBMIが目安となります。BMIの計算方法は「体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}」です。体重と身長から求められるBMIは、摂取エネルギーの過不足を知ることができます。
日本人の食事摂取基準(2020年版)には、目標とするBMIの範囲が示されており、65歳以上では「BMI21.5~24.9」です。18~49歳では「BMI18.5~24.9」、50~64歳では「BMI20.0~24.9」であることから、高齢者のBMIの下限は18~64歳と比べて高く設定されています。これは高齢者が低栄養傾向になると、フレイルのリスクが高くなるためです。健康維持のために、BMIにも注目してみることがおすすめです。
高齢者の中には、運動量によって栄養が不足しやすいのか気になる方もいるのではないでしょうか。下のグラフは、70歳以上のエネルギー摂取量とタンパク質量を身体活動レベルごとに示したものです。日頃の運動量が「低い・ふつう・高い」のシニアが、どれだけ栄養を摂っているかを表しています。
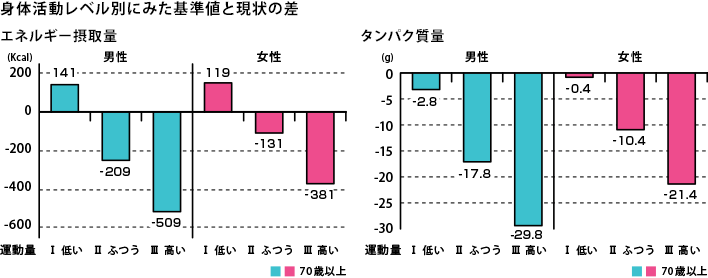
出典:清野隼.新たな食事摂取基準2015の概要 ~高齢者への栄養指導介入を見据えて~
日本ストレングス&コンディショニング協会機関誌 21(9), 8-13, 2014-11
グラフの結果では、運動量が高いシニアの方が「エネルギー摂取量」と「タンパク質量」が不足していました。このほかに摂取を意識したい栄養素としては、「カルシウム」や「
運動習慣のある高齢者は、体重が減少していないかを確認しながら、カラダに必要な栄養素も不足しないようにしていきたいものです。
50歳以上のタンパク質不足量は下記でも詳しく解説しています。
介護を必要としない健康寿命を延ばしていくには、カラダに必要な栄養素を摂取することも大切です。栄養不足は、高齢者のフレイルやサルコペニアのリスクが高くなります。
フレイルとは、「加齢に伴うカラダの機能低下によって、健康障害に陥りやすい状態」を指します。つまり、健康と要介護の間の状態です。また、サルコペニアとは「加齢に伴う筋力の減少または老化に伴う筋肉量の減少」を指す造語です。サルコペニアはフレイルの原因の一つでもあります。
高齢者が健康のために運動をしても、食事量が少ない場合には、カラダに必要な栄養素が不足するかもしれません。その結果、知らず知らずのうちに健康から遠ざかってしまう可能性もあります。
運動習慣がある高齢者で、体重が減少傾向にある場合は、運動後の栄養補給を意識してみてはいかがでしょうか。運動でカラダを消耗した状態からリカバリーするには、運動後に糖質やタンパク質を意識した栄養補給が必要になります。
カラダに必要な栄養素を摂取するには食事が基本となります。しかし、カラダを動かした後に食欲が湧かなかったり、少量しか食べられなかったりなど、食事からの栄養補給が難しい場合もあるかもしれません。このような場合は、手軽に食べられる「栄養補助食品」を利用することも方法の一つです。栄養補助食品の活用法を紹介します。
運動後はエネルギー源である糖質と、カラダづくりの材料になるタンパク質を摂取することで、カラダのリカバリーにつながるといわれています。タンパク質を摂取できる栄養補助食品はプロテインです。プロテインは、製品によって摂取できるタンパク質量や、そのほかの栄養素が異なるため、運動後は糖質とタンパク質を摂取できるプロテインを活用することがおすすめです。
カラダを動かすことは好きなのに、食が細くなって体重が減っていく方もいるかもしれません。食事からしっかりと栄養補給することが理想ですが、どうしても難しい場合は、栄養補助食品を利用することも選択肢となります。カラダづくりの材料となるタンパク質不足が気になる場合はプロテインで補ってみてはいかがでしょうか。プロテインはさまざまな形状があり、粉末プロテインやゼリー飲料などは運動後にも活用しやすいと思います。
スーパーマーケットやドラッグストアでプロテイン製品を見かけて気になっているものの、どれを選んだらよいのか迷ってしまう方もいるかもしれません。森永製菓が取り扱うプロテインの中から、おすすめの製品を紹介します。
大豆特有の香りや苦みがほとんどなく、軽くシェイクするだけで完全に溶けきるので、飲みやすいと感じる方もいると思います。1食あたりタンパク質が10.4g摂取できることに加え、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群も配合されています。アイスでもホットでも合うコーヒー味とビターカカオ味があり、日常生活に取り入れやすいのではないでしょうか。
プロテインを飲み続けると、味に飽きてしまう方もいるかもしれません。マッスルフィットプロテインは森永ココア味、バニラ味、森永ラムネ味、森永ミルクキャラメル味の4種類のフレーバーから選べます。
牛乳由来のホエイとカゼインの2種類を配合しており、森永ココア味では1食あたり23.3gのタンパク質を摂取できます。食事からタンパク質が不足している場合にも活用しやすい商品です。
大豆プロテインを配合しており、1食あたりタンパク質が15.6g摂取できます。カラダの調子を整えるビタミンCやビタミンB群、鉄も配合されています。健康維持にプロテインを活用したい方にも使いやすいのではないでしょうか。大豆プロテインはゆっくりと吸収されるため、満足感が持続して食事量が減ってしまう場合は、活用タイミングを調整して、食事はしっかりと食べることを優先させましょう。
1袋あたりタンパク質5gのほかに、カルシウムやビタミンB群も含まれています。爽やかなヨーグルト味で飲みやすく、粉末などを混ぜる手間もないため、手軽に摂取できるのではないでしょうか。脂質がゼロで、エネルギー量も低いため、タンパク質不足サポートのために活用しやすいと思います。
バニラ味のクリームをココア味のウェファーでサンドしたプロテインバーです。サクサクとした食感で、お菓子感覚で食べられるのではないでしょうか。1本あたりタンパク質10.7g、糖質9.9gで、運動後の栄養補給にも活用できます。サクサクしている分、口腔内に残りやすいため、水分も十分に飲みながら食べることがおすすめです。

高齢者の体重減少は、健康的なカラダから遠ざかってしまう可能性があります。運動習慣があり、体重が減少傾向にある方は、普段の食事量だけでなく、カラダを動かした後の栄養補給も見直してみてはいかがでしょうか。また、日常生活で運動習慣がなく、これから運動をしたいと思っている方は、運動を始める前に体調チェックを行い、転倒予防などの安全面を考慮して、無理のない範囲内で行ってください。
<参考>
日本ストレングス&コンディショニング協会機関誌 21(9), 8-13, 2014-11
プロテイン効果