MENU




【森永製菓】プロテイン公式サイト > 健康なカラダでいたい > プロテインを食事代わりにできる?プロテインの活用法


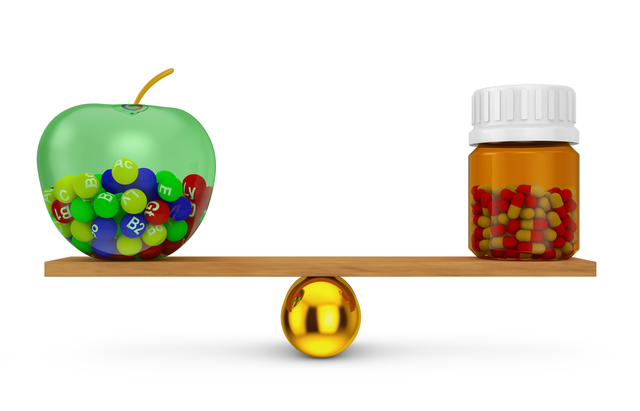
プロテインは、手軽にタンパク質を摂取できる栄養補助食品です。ダイエット中や理想のカラダづくり中には、摂取エネルギー量やタンパク質量の調整に向けて、プロテインを食事代わりにできないだろうかと考えたことがある方がいるのではないでしょうか。本記事では、食事とプロテインのそれぞれのメリットとデメリットを挙げ、プロテインの活用法を解説します。
※記事内でご紹介している森永製菓の製品の栄養成分は、2023年11月24日時点のものとなります。
ヒトのカラダは、寝ている間も心臓が動き、食べたものを消化するなど、常にエネルギーを使っています。また、食事から得た栄養素によってカラダの構成成分が新しく作られ、古くなったものは分解されたり排泄されたりします。ヒトが食事をするのは、生命を維持するためです。
プロテインは、あくまでもタンパク質摂取をサポートするものです。タンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルなど、ほかの栄養素を配合しているプロテイン製品もあります。しかし、さまざまな食材を使った食事と比べると、プロテイン製品で摂取できる栄養素やその量は限定されます。そのため、プロテインは食事の代わりにはなりません。カラダに必要な栄養素は食事から摂取することが基本です。

カラダに必要な栄養素を摂取するには、栄養バランスの整った食事が大切です。しかし、仕事や子育て、家事などに追われて余裕がない日は、食事の栄養バランスが偏る日もあるのではないでしょうか。
どうしても食事でタンパク質が摂取できない場合などに、プロテインで補うのは方法の一つです。食事とプロテインのメリット・デメリットを知ると、日々の食事とともにプロテインを活用しやすくなると思います。
【メリット】
【デメリット】
【メリット】
【デメリット】
競技のパフォーマンス向上のため、結婚式に向けてなど、減量をする目的はさまざまです。どのくらいの期間で、どのくらい減量をするのかは、目的によって異なると思います。ダイエット中の食事・栄養摂取のポイントをまとめました。
ダイエット前の通常の食事(3日~7日分)を振り返り、1日の摂取エネルギー量を把握することは方法の一つです。しかし、摂取エネルギー量の計算は難しそうだと感じるかもしれません。
最近では、食事記録をしながら摂取エネルギーの計算ができる無料のアプリがあるため、利用してみてはいかがでしょうか。アプリによっては、コンビニエンスストアや外食チェーン店で取り扱われている商品も登録されており、食べた量を入力すると自動で摂取エネルギー量を計算できます。
また、コンビニエンスストアやスーパーマーケットのお弁当やお惣菜などには、栄養成分表示があります。これらを購入する際には、摂取エネルギー量を確認することもおすすめです。
体脂肪1kgを減量するには、約7000kcalを消費することが必要です。体重の増減が1~2カ月ほどないとすると、この期間は摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスが取れていると考えられます。この状況から食事量の調整や活動量を増やすと、減量につながります。
減量のペースは個人によって異なると思いますが、急激な減量を行うとカラダの栄養不足が起こる可能性があります。メタボリックシンドローム改善の場合は、6カ月間で現在の体重の3~5%の減量で効果が期待できるといわれています。これを参考にして、減量ペースを設定するのもおすすめです。
例えば、80㎏の方の場合は、3~6カ月で2.5~4㎏減となります。80㎏の方が6カ月で4㎏減を目標にすると、7,000kcal×4㎏=28,000kcalを消費する必要があります。1日あたりにすると156kcalとなり、これを目安にして食事や運動を調整していきます。あらかじめ食事記録をしていると、食事量を減らすのか、運動を増やすのか、どちらも行うのかのように自分に合う方法が分かりやすいのではないでしょうか。
ダイエット期間は、無理のない範囲内で取り組みを行い、継続していくことがポイントです。なにかを我慢しながら無理をした取り組みをすると、反動でリバウンドする可能性があります。
ダイエット期間中にも誕生日などの特別な日があり、ごちそうを食べることもあると思います。また、雨が続いてウォーキングができないなど、イレギュラーなことがあるのではないでしょうか。このような場合は、摂取エネルギー量が多くなった日の次の日は運動時間を長くしたり、運動ができない日が続く場合は食事量で調整したりするなど数日の中で工夫しながら減量を行っていくことがおすすめです。

筋トレをして理想のカラダづくりを目指している期間は、カラダづくりの材料となるタンパク質の摂取を意識しているのではないでしょうか。筋トレ期間中の食事・栄養摂取のポイントをまとめました。
カラダに必要なタンパク質量は、年齢や性別、活動量、カラダの大きさなどによって異なり、個人差があります。1日に摂取したいタンパク質の推奨量は日本人の食事摂取基準(2020年版)に示されており、18~64歳の男性65g/日、女性50g/日です。また、摂取エネルギーに合わせた目標量も示されており、全年齢・男女で13~20%エネルギーです。
活動量が多い方、身長が高い方などは、カラダに必要な摂取エネルギーが多くなる傾向があります。そのため、摂取するタンパク質量は推奨量を満たしつつ、目標量を参考に調整することがおすすめです。
タンパク質は幅広い食品に含まれており、特に肉、魚介類、卵、大豆・大豆製品、乳・乳製品に多く含まれています。これらの食品は、タンパク質を構成するアミノ酸のバランスが良いことから「良質なタンパク質」と呼ばれています。食事メニューに良質なタンパク質を上手く組み合わせていくと、カラダに必要なタンパク質量を補いやすくなります。
筋トレ期間中はタンパク質摂取量を意識する方がいると思いますが、カラダを動かすために必要なエネルギー源となるごはん、パン、麺類なども適度に摂取することが大切です。
筋トレを行った若年者では24~28時間程度まで、カラダづくりが持続するといわれています。そのため、筋トレの期間は、カラダに必要なタンパク質を摂取し、栄養バランスの整った食事を意識するとカラダづくりにつながりやすくなると思います。
食事から摂取するタンパク質が不足する場合は、手軽に飲める牛乳や豆乳などを摂取するほか、プロテインを活用するのも方法の一つです。あくまでもプロテインは食事をサポートするものであり、食事からタンパク質を摂取することができれば、筋トレ期間に毎日飲む必要はありません。
普段の食生活でタンパク質不足が気になる場合、どのようなプロテイン製品が使いやすいのか気になるのではないでしょうか。森永製菓が取り扱うプロテイン製品の中から、おすすめをご紹介します。
マッスルフィットプロテイン 森永ココア味は、1食あたりのタンパク質23.3g、エネルギー113kcalの粉末プロテインです。18~64歳の男性のタンパク質推奨量は65gであり、この1/3量を摂取できます。配合されているタンパク質は、牛乳由来のホエイプロテインとカゼインプロテインです。
1食あたりのタンパク質は15.6g、エネルギー82kcalの粉末プロテインです。大豆プロテインが配合されています。また、摂取できるタンパク質量が15g以上でありながら、エネルギーも控えめであり、ダイエット中にも活用しやすいのではないでしょうか。
1食あたりのタンパク質は10g、エネルギー74kcalの粉末プロテインです。配合されているのは大豆プロテインであり、ゆっくりと消化されていきます。食事からのタンパク質不足が気になる日など、幅広い用途で活用しやすいと思います。
1袋あたりのタンパク質は15g、エネルギー112kcalのゼリー飲料です。粉末プロテインのように水や牛乳などに溶かす必要がないため、スポーツジムで栄養補給したい日、オフィスでの栄養サポートなどで活用しやすいのではないでしょうか。
1本あたりタンパク質は10.8g、エネルギー117kcalのプロテインバーです。ドライフルーツの入ったグラノーラがバータイプになっているため、ザクザクとした食感で食べ応えがあります。朝食が少なかった日の補助や、おやつ代わりに活用しやすいと思います。
カラダに必要なタンパク質は食事から摂取し、どうしてもタンパク質が不足する場合は、プロテインが選択肢の一つになります。食生活を振り返りながら、上手にプロテインを活用してみてはいかがでしょうか。
<参考>
1) 肥満症診療ガイドライン2022 第5章 参照日:2023年11月24日
2) 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)参照日:2023年11月24日
3) 日本人の食事摂取基準(2020年版)参照日:2023年11月24日
4) 筋肉量の増加に向けた効果的なレジスタンス運動とたんぱく質摂取 参照日:2023年11月24日
プロテイン効果
inゼリープロテイン15g